
令和5年度税制改正大綱での主な変更点とは?
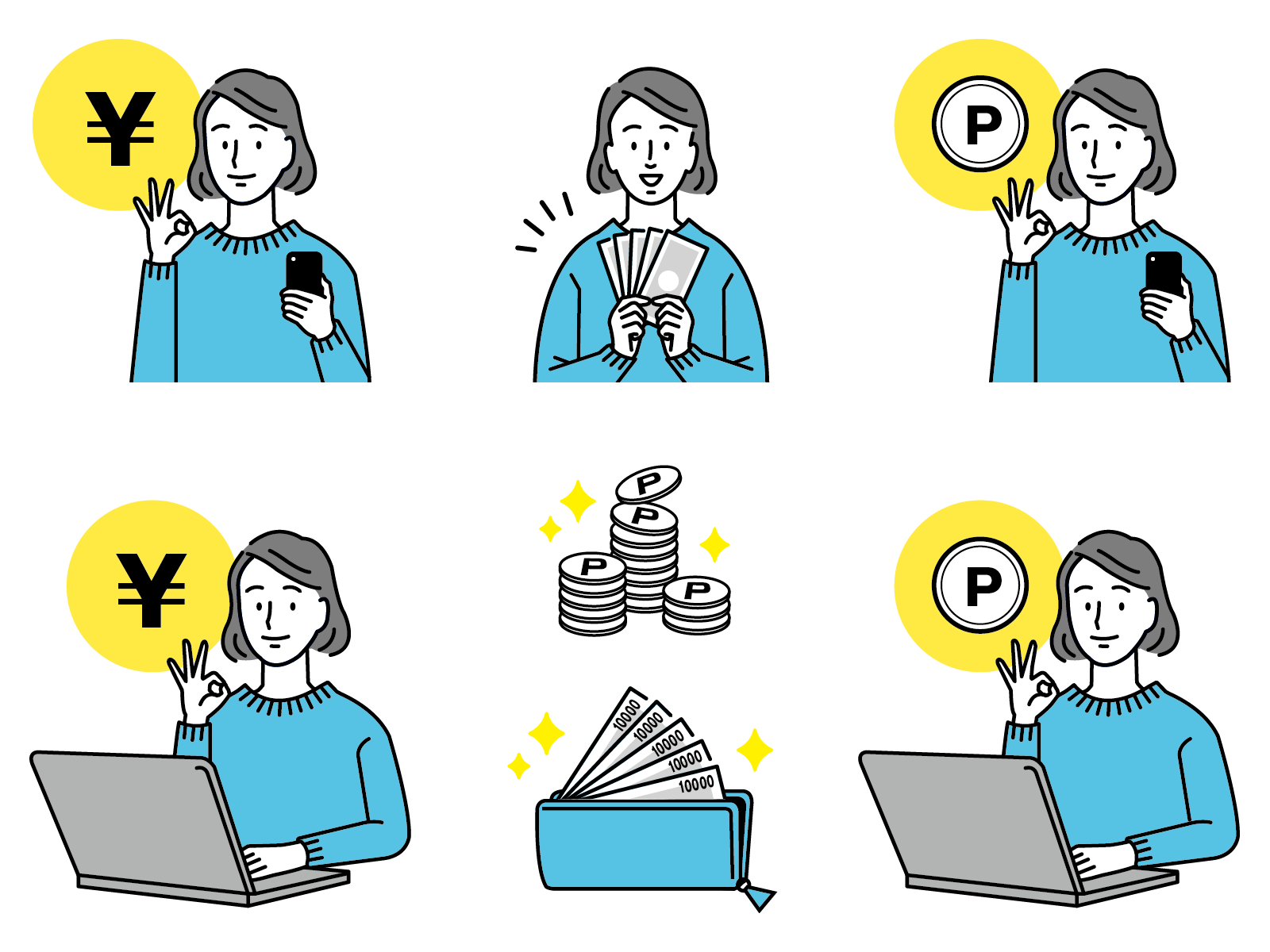
2022年12月に「令和5年度税制改正大綱」が発表されました。税制改正大綱では、財産を贈与するときに適用できる制度の内容や、生前に贈与された財産のうち、相続税の課税対象となるものの決まり方が変更されました。
また、まとまった資金を贈与するときに適用できる特例は、延長されたものがある一方で、終了予定とみられるものもあります。
今回は、令和5年度税制改正における主な改正点をご紹介します。
相続時精算課税制度の制度内容が一部変更
令和5年度税制改正大綱では、相続時精算課税制度の内容が変更されました。相続時精算課税制度は、60歳以上の父母や祖父母などが、18歳以上の子どもや孫などに財産を贈与するときに選択できる制度です。
現行の制度内容
1年間で贈与された財産の金額が110万円を超える場合、贈与税がかかります。そのため、不動産をはじめとした高額な財産やまとまった現金を一括で贈与すると、贈与税がかかりやすくなります。
相続時精算課税制度を適用すると、合計で2,500万円を超えるまで贈与税がかかることなく財産を贈与することが可能です。相続時精算課税制度により非課税で贈与された財産は、相続税の課税対象となります。
相続税よりも贈与税のほうが税率は高いです。そのため、高額な財産やまとまった現金などは、通常の贈与よりも相続時精算課税制度を適用する贈与のほうが、税負担を抑えられることがあります。
特別控除額である2,500万円を超える贈与には一律20%の贈与税がかかりますが、相続税を計算するときに納めた贈与税額を控除することが可能です。
新たに基礎控除が追加
相続時精算課税制度を適用すると、最大で2,500万円の財産を非課税で贈与できる代わりに、贈与税の基礎控除額である110万円が適用されなくなります。
相続時精算課税制度を適用すると取り消すことができません。適用後に、毎年110万円の基礎控除額の範囲内で財産を贈与したいと思っても元には戻せないため、制度の利用をためらう人は少なくありませんでした。
それが、改正後の相続時精算課税制度では、年間110万円の基礎控除が新設されました。これにより、相続時精算課税制度を適用したあとも、1年間で贈与された財産の額が110万円未満であれば、贈与税はかからず申告も不要です。
また、相続時精算課税制度の基礎控除額110万円分の贈与については、財産を贈与した人がなくなって相続が発生したとき、相続財産には加えられません。
相続開始前の生前贈与の加算期間が7年間に延長
1年間で贈与された財産の額が、贈与税の基礎控除額である110万円未満の場合、税金はかかりません。贈与を受ける人1名につき、年間110万円以内の贈与を繰り返して遺産を減らす「暦年贈与」は、相続税対策の1つとして多くの方に利用されてきました。
ただし、相続が開始される前の一定期間に被相続人から相続人に贈与された財産は、相続税の課税対象になるという決まりがあります。今回の税制改正で、相続税の課税対象となる生前贈与の期間が延長されました。
これまでは、相続が開始される前の3年以内に贈与された財産が相続税の課税対象でした。それが、2024年(令和6年)1月1日以降に発生する相続では「相続開始前の7年以内」の生前贈与が対象となります。
なお、相続が開始される4〜7年前に贈与された財産のうち、100万円は相続税の課税対象となる財産には含まれません。
改正により相続財産に加算される贈与財産は増える可能性
例えば、毎年100万円を10年(10回)にわたって息子に財産を贈与したあとに、父親が亡くなった場合、改正前は「100万円×3年=300万円」が相続財産に加算されました。
それが改正後は「(100万円×7年)-100万円=600万円」が相続財産に加算されます。
そのため、改正後に暦年贈与を用いた相続税対策をする場合、より早いタイミングで贈与を開始し、長い期間をかけて財産をわたしていく必要があります。
相続人以外に贈与された財産は引き続き相続財産には含まれない
相続財産に含まれるのは、被相続人から相続人へ生前に贈与された財産です。そのため、遺産を相続しない人に贈与された財産は、タイミングにかかわらず相続財産には含まれません。2024年(令和6年)1月1日以降に発生する相続においても、この点は同様です。
例えば、被相続人である父親が亡くなったときの法定相続人が妻と長男の2人であるとしましょう。長男には子ども(被相続人から見た孫)がいます。
父親が亡くなった時点で長男が健在である場合、孫は遺産を取得する権利はありません。そのため、相続が開始される7年以内に、被相続人が孫に生前贈与をしていたとしても、相続税の課税対象にはなりません。
資金を一括贈与したときの非課税の特例が延長に
教育資金や結婚資金、住宅取得資金を贈与する場合は、非課税の特例を適用することで一定金額まで贈与税がかからなくなります。主な特例制度は、以下の通りです。
- 教育資金の一括贈与の特例
- 結婚・子育て資金の一括贈与の特例
- 住宅取得等資金の一括贈与の特例
令和5年度の税制改正では、上記のうち1と2は延長が発表されました。
教育資金の一括贈与の特例と結婚・子育て資金の一括贈与の特例は延長
教育資金の一括贈与の特例とは、30歳未満の子どもや孫などに資金を贈与するときに、最大1,500万円まで贈与税が非課税となる制度です。
贈与された教育資金は、授業料や入学金などの支払いに充てられます。また、最大500万円までであれば、学習塾やスポーツ教室などの支払いに充てることも可能です。
結婚・子育て資金の一括贈与の特例は、18歳〜49歳の子どもや孫に、結婚や子育てのために使う資金を最大1,000万円まで非課税で贈与できる制度です。
贈与された資金は、結婚費用(挙式費用や新居の入居日など)や出産・育児費用(分娩費用や不妊治療にかかる費用など)の支払いに充てられます。ただし、結婚費用の支払いに充てられるのは、300万円が上限です。
令和5年度の税制改正により、教育資金の一括贈与の特例を適用できる期限が2026年(令和8年)3月31日まで3年間延長されました。結婚子育て資金の一括贈与については、2025年(令和7年)3月31日まで2年間延長されています。
住宅取得等資金の一括贈与の特例は終了予定
住宅取得等資金の一括贈与の特例は、住宅の新築や増改築などをするための資金を父母や祖父母などから提供してもらうとき、最大1,000万円が非課税となる制度です。
非課税となる贈与額は、断熱性能や耐震等級などが所定の要件を満たす省エネ等住宅が1,000万円まで、それ以外が500万円までとなります。
一方、住宅ローン取得等資金の一括贈与の特例は、令和5年度税制改正大綱に延長が明記されませんでした。そのため、2023年(令和5年)12月31日で終了する見込みです。
両親や祖父母からマイホームを取得するための資金援助を受ける場合、非課税制度を適用するためには、2023年末までに贈与してもらう必要があります。
相続空き家3,000万円控除の要件改正
相続空き家の3,000万円特別控除は、相続した空き家を売却するとき、売却益(譲渡所得)から最大で3,000万円を控除できる制度です。亡くなった人(被相続人)が作成した遺言書によって引き継いだ空き家を売却するときも、要件を満たせば適用できます。
令和5年度の税制改正大綱では、相続空き家3,000万円特別控除の対象が拡大されました。
これまで、特別控除を適用するためには昭和56年5月31日以前に建築された家屋を、売主自身が解体または耐震リフォームをしたうえで売却しなければなりませんでした。
それが2024年(令和6年)1月1日以降に空き家を売却する場合、売却した年の翌年2月15日までに買主が建物を解体または耐震改修をした場合も制度の対象となります。
また、空き家を相続する相続人が3人以上である場合、譲渡所得から控除できる金額が最大3,000万円から最大2,000万円に減額されます。
まとめ
- 2024年(令和6年)1月1日以降に「相続時精算課税制度」を適用して贈与する場合、贈与された財産の金額から基礎控除110万円を毎年控除できる
- 2024年(令和6年)1月1日以降は、贈与した人が亡くなったとき、相続開始前の7年前までに贈与された財産が相続税の課税対象になる
- 「教育資金の一括贈与の特例」と「結婚・子育て資金の一括贈与の特例」は延長されるが「住宅取得等資金の一括贈与の特例」は2023年末で終了予定
- 2024年(令和6年)1月1日以降に空き家を売却する場合、所定の期日までに買主が建物の解体または耐震改修をした場合も「相続空き家の3,000万円の特別控除」の対象
【コラム執筆者】

山本 健司
プロフィール
ミライアス株式会社代表取締役。大手不動産会社で全国1位の成績を連続受賞。不動産相談件数16,000件超。著書『初めてでも損をしない 不動産売却のヒケツ(サンルクス出版)』『損しない! モメない! 実家の不動産相続のヒケツ(サンルクス出版)』
